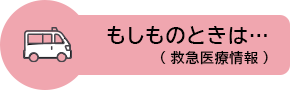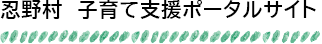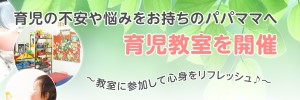本文
「葛根湯(かっこんとう)」雑談
山梨大学医学部附属病院血液・腫瘍内科 准教授 田中 勝
「葛根湯」という漢方薬を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。一般的にはかぜ薬として知られています。桂皮(けいひ)、芍薬(しゃくやく)、甘草(かんぞう)、大棗(たいそう)、生姜(しょうきょう)、麻黄(まおう)、葛根(かっこん)という7つの生薬からなるお薬です。西洋薬ではかぜのどの時期においても処方されるお薬は同じことが多いですが、漢方薬は罹ってからの時期やその方の体格や年齢、症状によって処方薬が異なります。葛根湯は、体格が比較的がっちりしていて、かぜの初期で汗が出ていない人に最も良く効く漢方薬です。かぜに罹ってからの日数が長いほど効きにくくなります。また、関節痛が比較的強く高熱があるようながっちりタイプのかぜの初期には麻黄湯(まおうとう)という薬がより適切です。その後、じわーっと汗が出てきたら柴胡桂枝湯(さいこけいしとう)というお薬にバトンタッチします。ただし、生薬の麻黄は交感神経刺激作用のあるエフェドリンが含まれており、あまり虚弱な人が内服するとムカムカ、ドキドキする副作用がでます。そんな人には麻黄の量の少ない麻黄附子細辛湯(まおうぶしさいしんとう)や麻黄が入っていない香蘇散(こうそさん)で対処します。その他にもかぜに使う漢方薬はたくさんあります。
前述した通り、葛根湯には生薬の葛根(クズの根)が入っており、鎮痛効果も発揮します。これを利用し発熱のない時の使い方として、肩こり(寝違え、むち打ち症を含む)、頭痛、三叉神経痛、腰痛、五十肩などに使われることがあります。また、乳汁分泌促進作用があり、産後の乳汁分泌不足に応用されることもあります。
漢方を専門とする先生方は、これまでお話ししてきたような症状、体格、年齢などだけではなく、舌を見たり(舌診)、脈をとったり(脈診)、お腹を触ったりして(腹診)、その患者さんに最も適切と考えられる漢方薬をチョイスしています。いわばこれらの診察で打率を挙げるといったところでしょうか。
今から約1800年も前の中国において葛根湯は作られました。落語の「葛根湯医者」は有名ですが、江戸時代を経て現代にいたってもなお処方され続ける、ちょっと不思議なお薬を紹介させて頂きました。