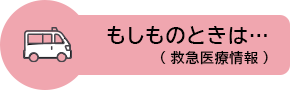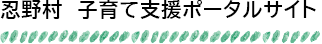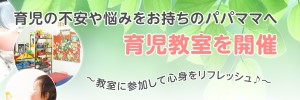本文
脈が跳ぶ?と感じたら…
山梨大学医学部附属病院 循環器内科 学部内講師 黒木 健志
心房細動という病気をご存じでしょうか。不整脈の一種であり、発症すると動悸・息切れ・めまいなどの症状が出て、ひどい場合は救急車を呼んで病院を受診される方もいらっしゃいます。一方で、健康診断を受けたらすぐに専門医にかかるように促されて、「どこも悪くないんだけれど」と目を白黒させて外来を受診される方もいらっしゃいます。病気には症状が顕著に現れていても実はそこまで心配いらないものもあれば、静かに住み着いて意外と性質の悪いものもあります。心房細動はそのどちらの顔も併せ持つ、なかなか奥深い病気です。心臓は血液を全身へ送り出すポンプの働きをしていますが、心房という補助ポンプと心室というメインポンプから成り立っています。心房細動になるとこの心房はポンプ機能を失いますが、心室は稼働し続けているため、通常血液の循環は保たれます。その場合患者さんは気を失うこともないですし、心房細動になったことすら気づかないこともあります。ただしこの心房が働かない状態が続くと、心房の中の血液は滞り、血栓という血の塊ができやすくなってしまいます。さらにこの血栓が心房から剥がれて心臓から外へ送り出されると、深刻な症状を引き起こす可能性があります。元読売巨人軍監督の長嶋茂雄さんも、この心臓の血栓が原因で脳の血管が詰まり脳梗塞を発症したといわれています。現役バリバリで社会貢献をされているような方がある日突然半身不随になってしまう。それが心房細動の怖いところです。
脈の乱れが気になったら早めの受診をお勧めします。それからくれぐれも年1回の健康診断は必ず受けるようにしてください。心房細動が診断されれば、抗凝固薬を飲むことで脳梗塞は予防可能です。さらにカテーテルアブレーションという治療もあり、1年程度の持続であれば心房細動は十分根治も望める疾患です。どんな病気でもそうですが、早期発見、早期治療が重要です。さらに言うと予防に勝る治療はありません。心房細動の発症も生活習慣との関わりが知られています。皆さんも「リンゴ型肥満」や「洋ナシ型肥満」という言葉をお聞きになったことがあるかもしれません。それぞれ内臓脂肪型肥満、皮下脂肪型肥満とも言います。この内臓脂肪というのが実は結構曲者で、心房細動もこの心臓の周りの内臓脂肪が増えると発症しやすくなります。内臓脂肪型肥満は男性に多いのですが、女性も閉経すると内臓脂肪型へ移行しやすくなります。食事は腹八分にとどめ、お散歩には毎日行きましょう。