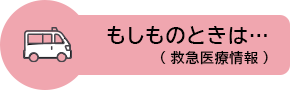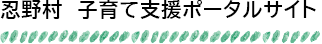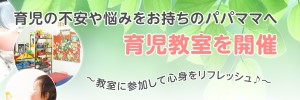本文
百薬の長とはいえど
山梨大学医学部附属病院 消化器内科 特任講師小林 祥司
「酒は百薬の長」とは、今からちょうど2,000年前の中国の“新”時代の文言にその由来があるといわれています。特に医学的に根拠があったものではないと思いますが、永きにわたり多くの酒飲みを励ましてくれた言葉でしょう。1981年には「Jカーブ効果」と呼ばれる疫学調査が発表され、適量のお酒を飲むことが総死亡率を低下させるといった効果が知られることとなりました。(限定的なもので、飲酒を推奨するものではありません)
お酒の適量とはどのくらいでしょうか。通常のアルコール代謝能力を持った男性の場合、1日平均で純アルコール20グラム程度です。女性や65歳以上のかたなどはその2分の1~3分の2程度がよいようです。また、すぐに顔が赤くなるかたは赤型体質と呼ばれ、アルコール代謝能力が低く、やはり飲酒量は減らしたかたがよいです。アルコール20グラムとはそれぞれ、ビールなら中瓶1本、日本酒なら1合、酎ハイ(7パーセント)なら350ミリリットル程度です。全部ではなく、それぞれでの量です。少ないと感じますが、それが適量です。
それでは、過量の飲酒が及ぼす健康リスクとはどのようなものでしょうか。肝硬変や肝がん、すい臓がんが有名ですが、高血圧、脳出血、脂質異常症(高脂血症)、高尿酸血症(痛風)、脳梗塞、虚血性心疾患(心筋梗塞)、糖尿病など、枚挙にいとまがありません。また、身体の健康だけでなく、事故や暴力、虐待などの社会問題にも関わってきます。
私の専門の話をしますと、先述の赤型体質のかたで適量を超えて飲酒をされるかたは、食道がんの発症のリスクが何10倍にもなります。アルコールの代謝物質であるアセトアルデヒドには、発がん性があることが明らかになっています。すぐに顔が赤くなるかたはアセトアルデヒドを無害な酢酸に分解する能力が弱く、長く体内に残ることで発癌のリスクが上がります。もちろん赤くならずとも、量が増えれば発癌のリスクは上がります。いずれにしても、定期的に胃カメラなどの検診を受けることをお勧めします。
「百薬の長とはいえど、万の病は酒よりこそ起これ(吉田 兼好)」お酒とは万能薬ではなく、健康リスクを有するものです。そろそろ秋も深まり、秋あがりやヌーボーの季節でしょうか。「ときには我を忘れるほど酔うことも人間の特権だ。(山本 周五郎)」ですが、適量を守り(ワインは200ミリリットル程度です)、食事とともにお酒を嗜んでいただければと思います。休肝日をつくることもお忘れなく。健康にはくれぐれもご留意ください。