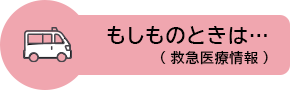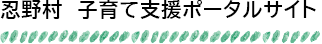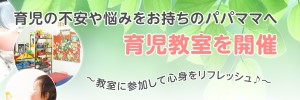本文
治りにくい蓄膿(ちくのう)症-好酸球性副鼻腔炎-
山梨大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科助教 代永孝明
蓄膿(ちくのう)症という病気を聞いたことがあるかもしれませんが、正しい病名は副鼻腔炎(ふくびくうえん)といいます。目の下や目の内側、おでこの裏側などには空間があり、その場所を副鼻腔といいます。そこに細菌やカビ菌、ウイルスなどが炎症を起こして蓄膿、つまり膿が溜まることで痛みを生じたり、黄色い鼻水が出たり(膿性鼻汁)、膿がのどにまわったり(後鼻漏)するなどの症状を起こしている状態が副鼻腔炎です。抗生物質の薬を飲むことにより大半の副鼻腔炎は治るようになりました。
しかし、近年では薬でなかなかよくならない副鼻腔炎が増加しています。それが題名にある好酸球性副鼻腔炎です。好酸球とは血液中に含まれる白血球の仲間ですが、その好酸球が鼻の粘膜にたくさん出てきて、強い炎症を起こしている状態のことを指します。主な症状としては嗅覚障害、つまりにおいがわからなくなります。においを感じる神経やその周りの粘膜に炎症を起こし、においを感じなくさせているのです。また、鼻の粘膜がむくんでポリープがたくさんできることにより、鼻づまりを起こすこともあります。さらに喘息を一緒に起こしやすいといわれており、これらの症状により患者さんの生活の質は大変悪くなります。
診察の結果で好酸球性副鼻腔炎が疑われたら、まずは炎症を抑える飲み薬や点鼻薬の治療からはじめます。あまりよくならない場合は、次の一手として内視鏡を使った鼻の手術が行なわれます。手術をしてすっきりよくなる場合もありますが、非常に再発しやすい病気ですので安心はできません。手術の後も再発させないように、薬でうまくコントロールしていく必要があります。近頃は自己注射薬の使用が国から認可され、よい状態を保てる患者さんも増えてきました。
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、嗅覚障害が注目されています。においを感じなくなっても直接命に関わることは少ないですが、においのない生活は味気ないものです。もし思い当たる症状があれば、一度お近くの耳鼻咽喉科を受診して相談していただくことをお勧めします。