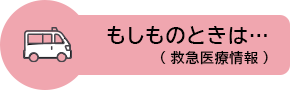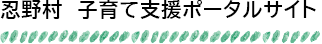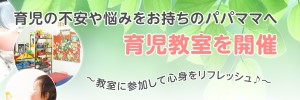本文
子育てにまつわる忍野村の風習
忍野村の子育てにまつわる風習をご紹介します。
神鋏(かんばさみ)
赤ちゃんの健やかな成長を願って、親族の中の女性が赤ちゃんの髪の毛を切る風習です。最近ではお宮参りをする日に行うことが多いです。
用意するのは金属製のハサミと、桑の木から作った箸2膳。古いしきたりでは、神棚へのお供え物として洗米、茶葉、塩を丸いお盆の上に置いた半紙の上に並べます。
神鋏では、赤ちゃんの髪にハサミを入れられるのは女性のみ。参加する人数は縁起の良い奇数。だいたい7人か9人が車座になります。母親は赤ちゃんを抱いて車座を順番に回っていきます。
赤ちゃんの祖母からスタートし、その後は血縁関係が近い人から順にハサミを入れます。
赤ちゃんを前にした参加者は、まず桑の木で作った2膳の箸で、それぞれ1回ずつ髪の毛をはさみます。最後に金属のハサミでほんの少しだけ髪を切り、切った髪の毛はお供え物と一緒にまとめます。
お箸やハサミを持つ際、参加者は赤ちゃんに「元気に育つんだよ」「お母さんの言うことをちゃんと聴きなさい」と声をかけます。全員がハサミを入れたら終了となり、髪の毛は洗米、茶葉、塩を置いた半紙の上に置いて神棚にお供えします。
最近では神鋏を行う家も少なくなってきたものの、忍野村で古くから続く風習として大切に受け継がれています。ちなみに儀式に参加しない男性は、車座の後ろでその様子を見守っています。
立ち餅(たちもち)
赤ちゃんが立って歩くようになった際、各家庭で行われる風習です。
立ち餅が行われるのは、赤ちゃんが2~3歩進めるようになった日の週末。その日は朝から家の男性が餅をつくことになります。
つきあがったお餅が冷えたら、風呂敷にくるみ、赤ちゃんにたすき掛けします。そして、親たちは赤ちゃんと向き合い「餅を背負ってこっちにおいで」と声をかけ、4~5歩進めたら成功。
背負ったお餅を家庭で食べます。家によっては、ついたお餅に赤ちゃんの足型をつける場合もあります。体の小さな赤ちゃんにとって、お餅は大変重たいもの。背負ったままひっくり返ることもしばしばあるため、両親にとってはハラハラドキドキの時間です。
最近ではお餅ではなく、大福をリュックに入れて背負わせることもあるようです。形を変えながらも、古くからの風習は脈々と続いています。
- 風習には諸説あります。