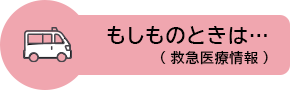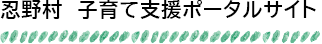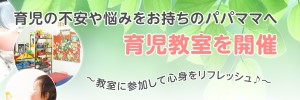本文
骨粗鬆症について
山梨大学医学部附属病院 整形外科 講師 安藤 隆
骨粗鬆症とは、骨の量(骨量)が減ってくることによって骨が弱くなり、骨折しやすくなる病気です。日本には約1000万人以上の患者さんがいるといわれており、山梨県でも6万人以上の患者さんがいることになります。そして、高齢化社会を迎え、その数はますます増えています。
骨の量が少なくなっても、痛みなどの症状はほとんどありません。それでも、転ぶ、ひねるなどのことで骨折しやすくなっています。骨折しやすいのは、背骨、太ももの付け根の骨、手首の骨などです。当然、骨折すると、その部分がとても痛く動けなくなります。また、背骨の骨折の場合は、背中や腰が痛くなり、その後に、背中が丸く(前かがみに)なったり身長が縮んだりします。あまりに背中が曲がると、おなか(胃)が圧迫され、ご飯がうまく食べられなくなってしまう人もいます。
骨は、体を支えてくれる重要なものです。体の外からは見えませんが、見た目には同じようでも骨は生きていて、常に新陳代謝を繰り返しています。古い骨を溶かして(骨吸収)カルシウムに戻し、そのカルシウムを新たに骨にすること(骨形成)が体の中で毎日起こっています。骨粗鬆症は、このバランスが崩れることが原因で、骨の量が減ってだんだんスカスカになってしまいます。
骨粗鬆症は圧倒的に女性、特に閉経後の女性に多くみられ、女性ホルモンの減少や老化と深い関わりがあります。骨粗鬆症は予防することが大切な病気です。食事では、カルシウム(牛乳、豆腐、小魚)を十分に、ビタミンD(魚)、ビタミンK(納豆・海藻)、リン、マグネシウムと適量のタンパク質(肉・魚)を取ることが大事になります。また、運動をすることで筋肉も骨も強く保たれ、転んだり、骨折したりしにくくなります。日光浴はビタミンDの力を強め、カルシウムを多く骨に取り込むことができるようになります。最後に、いつまでもいい骨でいるためには禁煙し、アルコールは控えめにするようにしましょう。
骨粗鬆症の検査は、血液検査、X線(レントゲン)、超音波法、CT法といろいろありますが、骨の量や成分(骨密度)を測定するためには、DEXA(デキサ)法が必要になります。もし、町の検診や簡単な検査で骨粗鬆症かもしれないとの結果が出たときや、骨粗鬆症の気になる年齢になったときは、整形外科の受診をおすすめします。