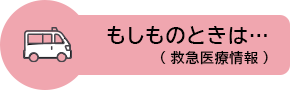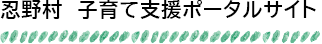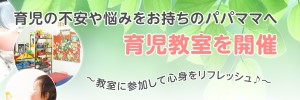本文
こどもの心臓病
山梨大学医学部附属病院 小児科学講座 助教 喜瀬 広亮
「こどもの心臓病」というと"大変な病気"というイメージで、あまり馴染みのない方も多いと思います。今回は、そんな「こどもの心臓病」についてのお話です。
こどもの100人に1人は心臓の病気を持って生まれてくると言われています。山梨県の出生数は、今現在年間6000人前後ですので、1年間に約60人のこどもが心臓に問題を抱えて生まれていることになります。近年では、医療技術の進歩や検診の普及によって、県内でも出生後の早い時期、場合によっては出生前に診断がつくことも多くなってきています。治療に関しても、これまで侵襲の大きい外科手術が中心であったのに対して、必要に応じて低侵襲な(身体への負担の少ない)手術や心臓カテーテル治療を行うことで、安全な治療が可能になってきています。
一方で、これから解決していかなければならない問題もあります。以前は治療が困難であったこどもの心臓病が助かるようになり、大変な治療を無事乗り越えて成人される方が年々増えてきました。こうした病気の約半数は、年齢を重ねるに従い様々な問題を生じてくるため、治療後も定期的な通院が必要で、成人してから治療が必要となることもあります。平成29年の時点で、こどもの頃からの心臓病(先天性心疾患)を有する方は、国内で90万人おり、同年の成人の心疾患(高血圧を除く)の患者数173万2千人と比べ決して少ないとは言えず、さらに、こうした方は今後急激に増えていくことが予想されます。しかし、今現在、日本国内でこうした方々をサポートしていく医療体制が十分には整っていません。今後、こどもの心臓病を診る小児循環器医と成人の心臓病を診る循環器内科医、心臓の手術をする心臓血管外科医がチームを組んで診療体制を整えていく必要があります。さらに、成人後は心臓が原因で他の臓器にも様々な問題が生じる可能性があるため、消化器内科、腎臓内科、産婦人科、神経内科、精神科等複数科のサポートが不可欠です。しかも、仕事や家庭の事情で地域を移動される方も多いため、各医療機関の中でも先天性心疾患への理解を深めていきながら、県内・県外の病院間で連携を図っていく必要があります。山梨県内では、山梨県立中央病院と山梨大学附属病院で、こうした成人された先天性心疾患の方の外来を開始しています。
こどもの頃から多くの職種と家族の協力のもと、大変な治療を乗り越えて、ようやく家族のもとで生活できるようになったこどもたちが、成人後も安心して社会で生活を送れるよう、山梨県内でも成人後の先天性心疾患の方の診療体制を構築していく必要があります。本稿をお読みいただき、こどもの心臓病の現状について、少しでも知識を深めていただければ幸いです。