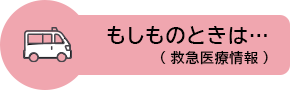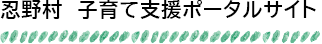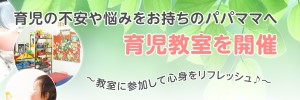本文
後発医薬品の使用について
山梨大学医学部附属病院 薬剤部長 鈴木 正彦
わが国の医療関係給付費は、少子・高齢化など人口動態の変化や高額な新医薬品・新医療技術の保険収載などにより年々増加し、2018年度には39兆円を超えると予測されています。
医療の質を落とすことなく医療関係給付費を抑えるためには,後発医薬品の使用促進が必須であるとして2017年6月の「経済財政運営と改革の基本方針」にて、2020年9月までに後発医薬品使用割合(注1)を80%まで引き上げることが閣議決定され、国・都道府県などが連携して様々な対策が施行されてきました。この結果、全国平均の後発医薬品使用割合は、2013年度の47.9%から2018年9月期には75.3%に徐々に上昇しています。
山梨県でも県・市町村が連携して様々な対策を施行していますが、山梨県の後発医薬品使用割合は、2017年9月期63・6%(47都道府県中46位)、2018年9月期71.5%(同44位)と低く推移しています。山梨県内を対象とした様々な解析によりますと、疾患別解析では、アレルギー疾患、呼吸器疾患、感染症の疾患グループにおいて後発医薬品の使用割合が低く、年齢層解析では7~14歳が最も低く小児および高齢者における使用割合が低いとされています。また、地域別解析では、昭和町63.6%、中央市64.6%と、この広報誌が届けられる地域での使用割合が低いとされています。
患者様の中には、「安かろう・悪かろう」の意識から「安い薬=効果のない薬」と考えられ、後発医薬品の服用に難色を示される患者様もおられます。
後発医薬品企業は、後発医薬品を販売するにあたり「カプセル剤を錠剤に変えたり、錠剤を小型化したり、口腔内で溶けやすい錠剤にしたり、粉薬の味や臭いを改善するなどして服用性を改善する」、「錠剤やカプセル剤に直接医薬品名を印字して識別性を改善する」、「冷所保存から室温保存にするなど保管条件を改善する」など、様々な工夫をして付加価値を高めています。
後発医薬品の使用促進が喫緊の課題であっても、病気を治療する患者様の気持ちが最優先であり「薬を変える事への不安」と「今は症状が安定しており、できれば薬を変えたくない」との気持ちを否定するものではありません。
後発医薬品の効果の同等性については国が保証しておりますので、今後「新たに薬の服用を始める場合」や「服用している薬が飲みにくいと思われた場合」には、医師や薬剤師に後発医薬品の使用について相談をしていただけますようお願いいたします。