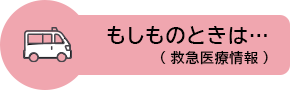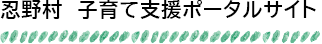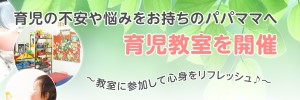本文
進化と歯
山梨大学医学部附属病院 歯科口腔外科 講師 諸井 明徳
歯は目で見ることが可能な口腔内にある組織であるため、美容目的での歯列矯正または審美修復治療が行われることもしばしばあります。このように他人の目にも、自分の目にもよく触れる歯ですが、人間の進化の一端が見てとれることはあまり知られていません。
無脊椎動物は歯を持っておらず、進化をしながら脊椎動物になり、その後に哺乳類が誕生しました。その中から6500万年前に原猿目、広鼻猿、狭鼻猿、そして類人猿へと進化をしていきました。その歯の本数は、原猿目は38本、広鼻猿は36本、狭鼻猿は32本、そして類人猿32本となり、ホモ・サピエンスも32本です。哺乳類全体ではモグラなどの44本の歯が基準となっていますから、私たちの祖先は、立位歩行や脳の増大などの大きな進化と共に歯の数を減らしてきたことになります。このように進化の過程で機能などを退化させていくことを「退化的進化」と言うそうです。
さて、私たち現代人において歯の本数はどうなっているでしょうか。現代人の歯数は28本~32本とされています。単純に歯が減ることを退化的進化とするのであれば、私たちは今まさに進化の途中に立ち会っているのかもしれません。では、どの歯にその進化がみてとれるのでしょうか。これまでの調査からも歯の数が減っていくことや小さく形を変えていくのは、歯並びの端から起こることが分かっています。つまり、一番奥の歯で歯が生える人もいれば、歯が生えない人もいる歯と言えば、「親知らず」です。
「親知らず」の正式名称は第三大臼歯と言い、20歳前後に生えてきます。親が生えるのを見ることがないことから親知らずと呼ばれ、海外では知恵がそなわってから、歯が萠出(ほうしゅつ)するのでwisdom teeth「智歯(ちし)」と呼ばれたりします。「親知らず」は、人間の進化を私たち自身に実感させてくれる非常に貴重な存在なのです。しかし、私たちの生活において「親知らず」と言えば、「親知らずが痛い」や「萠出してきたから歯並びが悪くなった」など悪いイメージがつきまといます。この進化の狭間の産物の問題解決に手助けをできるのは、人間の進化の中で生まれた医療です。口の中にはこの他にも不思議なことがたくさんあります。口の中に興味を持っていただき、人類進化の一端を皆さんと私たち医療人とでよく観察しながら、ついで口の中の健康も維持していきましょう。