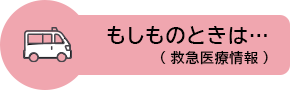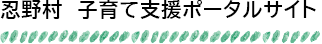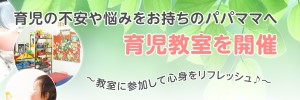本文
こどもの難聴
山梨大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 臨床助教 高橋 真理
皆さんは「難聴」という言葉から、どんな患者さんを想像しますか?多くの方は、70代、80代と年齢を重ねた患者さんを想像するのではないでしょうか。確かに、どんなに健康な人であっても、個人差はありますが、年齢の変化で音や会話の聞き取りにくさが出てきます。では、こどもの難聴はないのでしょうか?今回は小児難聴についてお話させていただきます。
生まれつき両方の耳の聞こえが悪いこどもは、1000人あたり1〜2人と言われています。山梨県の出生数は6000人くらいなので、計算上は毎年数人の両側難聴のこどもが誕生するのです。赤ちゃんの頃は音に対する反応が分かりにくいため、以前は2〜3歳になっても言葉が出ないことで、難聴が発見されるケースが多くありました。言葉を覚えるうえで1〜3歳は非常に重要な時期なので、発見が遅れると、その後の言葉の発達に大きな影響を与えてしまいます。そこで難聴の早期発見のために導入されたのが、新生児聴覚スクリーニングです。これは、出生後に簡易な脳波の検査などをして難聴が疑われるかどうかをみる検査です。山梨県の全産科施設で実施されていて、任意の検査ですが95%前後のお子さんが受けています。以前は検査の費用は全額自己負担でしたが、最近では市町村からの補助が出るようになっています。そこで難聴が疑われた場合には、検査を重ねて診断を行います。その結果で、補聴器などの介入を相談していく必要があります。
では、新生児聴覚スクリーニングを受けて、パスしていれば心配ないのでしょうか?残念ながら、検査をすり抜けてしまうことも、ごく稀ですがあります。生まれたときに問題なくても、難聴が進行してくるケースもあります。また、滲出性中耳炎(しんしゅつせいちゅうじえん)といって、鼓膜の奥に水が溜まってしまい聞こえが悪くなる中耳炎は非常に多くのお子さんがかかってしまいます。そういったケースを見逃さないために、市町村の検診でも聴力評価を行っています。
日常生活で重要な、「言葉」を覚えるために、難聴の早期発見はとても重要です。おうちでの生活で、「この子は聞こえが悪いかもしれない」と感じることがあれば、まずは耳鼻科を受診して相談してみることをお勧めいたします。