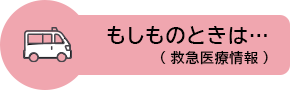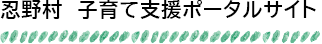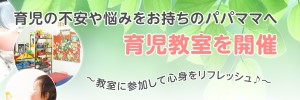本文
複数の「アレルギー疾患」を一か所で
山梨大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 准教授 上條篤
皆さんは「アレルギー疾患」と聞いて、どんな疾患を思い浮かべますか?花粉症、気管支喘息(ぜんそく)、アトピー性皮膚炎、蕁麻疹(じんましん)、食物アレルギー、ハチ毒アレルギー、薬剤アレルギーなど、様々なアレルギー疾患がありますよね。実は、近年そのほとんどが増加傾向にあるんです。
皆さん、花粉症はありませんか?地域によっては、なんと2人に1人が花粉症を発症していると言われています。「花粉症だけですか?気管支喘息もお持ちでは?食物アレルギーはどうですか?」そう、1人で複数のアレルギー疾患を患っているかたも少なくありません。そんな時、どうしていますか?
今までは、アトピー性皮膚炎があれば皮膚科、気管支喘息があれば呼吸器内科、食物アレルギーは小児科というように、個々のアレルギー疾患に対応した診療科を受診することが多かったのではないでしょうか。必ずしも悪いことではありませんが、その現状に不便さを感じているかたかたもいらっしゃるかもしれません。実は、日本のアレルギー専門医の数は決して多くありません。ちなみに、山梨県のアレルギー専門医は平成29年10月現在、17人にすぎません。もちろん、アレルギー専門医でなくても自ら勉強し、正しい診療をしてくださっている医師もたくさんいらっしゃいますが。とにかく、皆さんに正しいアレルギー疾患の知識を提供し、治療を受けていただくことは、我々の責務だと思っています。
山梨大学では、平成29年7月から「アレルギーセンター」を開設しています。アレルギーセンターでは、様々なアレルギー疾患に対応できる体制となっています。特に最近では、食物アレルギーの方の受診が増えています。現在、小児科と協力して、食物アレルギー患者さんの食物負荷試験が施行できるように準備しています。小児の食物アレルギーは、従来、原因食物の除去が主体でした。しかし、最近では食物負荷試験によって、食べられる量を決定し、外来で少しずつ食べて体を慣らしていく方法も行われるようになってきています。まだ、必ずしも方法論が確立しているわけではありませんが、少しずつ食べられる量が増えてきているお子さんも確かにいらっしゃいます。食物アレルギーと言えば、最近のトピックスとして、「アレルギーの感作は皮膚から始まる」という説があります。皮膚が荒れていると、そこからアレルギー物質が体内に侵入し、その物質に対してアレルギー反応を起こすようになるという説です。皆さん覚えているでしょうか?「茶のしずく石鹸」を使っていたご婦人が、小麦のアレルギーになるという事例が社会問題となっていましたよね。「茶のしずく石鹸」には加水分解小麦が含有されていたため、それが顔の皮膚から吸収され、小麦のアレルギーを発症したというわけです。少し、話が脱線しましたが、「アレルギーセンター」では複数のアレルギー疾患に対応可能です。受診希望のかたは、お近くの医療機関の紹介状をお持ちになってくださいね。