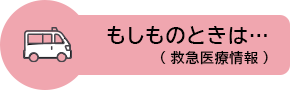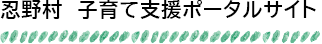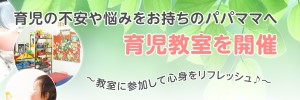本文
食中毒予防 -3つの原則-
山梨大学医学部附属病院 看護部管理室 感染管理認定看護師 矢崎 正浩
気温が高くなり始め、湿度も高くなる梅雨時は、細菌による食中毒が増えます。細菌は温度と湿度などの条件が揃うと食べ物の中で増殖し、ヒトがその食べ物を食べることにより食中毒を引き起こします。原因となる細菌の代表的なものは、腸管出血性大腸菌(O157、O111など)やカンピロバクター、サルモネラ属菌などで、乳幼児や高齢者では重症化する場合もあり注意が必要です。
食中毒の原因となる細菌は目に見えないため、どこにいるか分かりません。私たちの周りのいたるところに存在している可能性があります。肉や魚などの食材、いろいろな所に触れる自分の手、きれいにしているキッチンでも食器用スポンジや布巾、まな板などには細菌が付着し増殖している可能性があります。
細菌による食中毒を防ぐためには、細菌を食べ物に「つけない」、食べ物に付着した細菌を「増やさない」、食べ物や調理器具に付着した細菌を「やっつける」という3つが原則となります。
「つけない」…調理前に肉・魚・卵を取り扱う前後、食卓につく前には、必ず手を洗いましょう。生の肉や魚を切った包丁やまな板などの器具から、加熱しないで食べる野菜などへ菌が付着しないように、使用のたびにきれいに洗うことも大切です。焼肉などの場合には、生の肉をつかむ箸と焼けた肉をつかむ箸は別のものにしましょう。食品を保管する際は、周囲の食品から細菌が付着しないように、密封容器やラップをかけて保管します。
「増やさない」…細菌の多くは10度以下では増殖がゆっくりとなるため、低温で保存することが重要です。総菜や生鮮食品は、購入後できるだけ早く冷蔵庫に入れましょう。冷蔵庫に入れても細菌はゆっくりと増殖するので、早めに食べることが大切です。
「やっつける」…ほとんどの細菌が加熱によって死滅しますので、肉や魚はもちろん、野菜なども加熱して食べれば安心です。とくに肉料理は中心部までよく加熱することが大切で、中心部を75度で1分以上加熱することが目安となります。肉・魚・卵などを使った後の調理器具は細菌が付着しているため、よく洗ってから熱湯をかけて殺菌すると効果的です。
最後に、嘔吐や下痢の症状は、原因物質を排除しようという体の防衛反応です。むやみに市販の下痢止めなどの薬を服用せずに、早めに医師の診断を受けましょう。