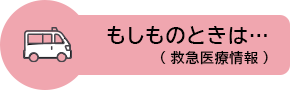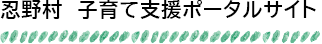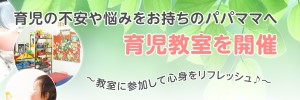本文
優しい外科治療
山梨大学医学部附属病院第1外科教授 市川大輔
皆さんは外科手術と聞くと、どのようなものを想像されるでしょうか。最近では、色々なメディアで紹介されることもあるので、腹腔鏡(ふくくうきょう)手術という言葉を聞いたことがあるかたもおられると思います。
お腹に1センチメートル程度の孔(あな)を幾つか開けて、二酸化炭素でお腹を膨らませた後に、挿入したカメラによってモニター画面上に臓器を映し出し、鉗子(かんし)というマジックハンドのような道具を用いて悪い部分を治す手術のことです。手術の内容は、20センチメートル以上切って行う従来の開腹手術と原則として同じであり、手術中の出血量が少ないことや、手術後の傷が小さいこと、痛みが少なく回復が早いことなど、患者さんに優しいことが大きなメリットです。
この手術は外科医にとっても優しい手術であることが知られています。まず第一に、カメラを近付けることで、手術を行う部位を拡大して見ることが可能になります。また、通常は一方向からしか見ることが出来ない部分も、様々な方向から観察したり切ったりできるのも大きな特徴です。最近では、4Kや8Kといった高画質での手術や、遊園地や映画などでもご存知の3D画像による立体視での手術も可能になりました。しかしながら、マジックハンドのような真っ直ぐな鉗子(かんし)という道具を用いて手術を行うため、鉗子(かんし)が届く範囲に制限があることや、外科医の手の震えなども問題となることがあります。
それら腹腔鏡手術の弱点を克服するために開発されたのがロボットによる手術です。ロボット手術と聞くと、ロボットが自ら考えて自動的に悪いところを治すように感じられますが、実際はロボットによる支援のもとに行う腹腔鏡手術です。ロボット手術で用いる鉗子(かんし)は自由自在に動く関節の機能を持っているため、これまで通常の腹腔鏡手術で届かなかった場所にも、容易にアプローチすることができます。また、高解像度の3D画像を見ながら、手振れ防止の機能を持った精密に動く鉗子(かんし)で行う手術によって、手術後の合併症の減少が報告されており、極めて質の高い安全な手術の実現が期待されています。
山梨大学医学部附属病院では、より患者さんに優しい外科治療の実践と臓器の機能をできる限り温存するような新たな治療についても積極的に行うことで、「世界トップレベルの医療を山梨へ」をモットーに地域医療に貢献しております。