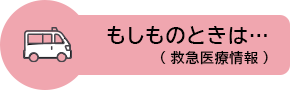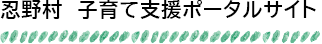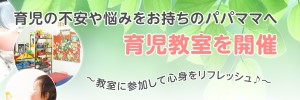本文
病院で行われてる輸血療法 ~ 安全・安心を第一に ~
山梨大学医学部附属病院 検査部 輸血検査室 臨床検査技師 中嶋 ゆう子
『輸血』と聞くと医療ドラマの手術室でバシャ! と出血し、執刀医が『輸血急いで!』というシーンや、白血病などの病気の患者さんへ投与するイメージでしょうか?また、『血液型』と聞くと相性占いや性格診断、親子鑑定などを思い浮かべますか? 輸血(輸血療法)は手術・ケガ(急性の出血)や病気や治療の過程(慢性的な貧血)で不足した血液成分(赤血球・血漿・血小板)を、日本赤十字社の献血(同種血と呼びます)または、患者さんご自身(自己血と呼びます)の血液成分を用いて補充する『補充療法』です。赤血球が不足すると全身の細胞が酸素不足になり、息切れや動機・だるさやめまいなど貧血症状が起きますし、血漿中の凝固因子や血小板が不足したり機能しないと、出血しやすくなり、ぶつけていないのにあざができたり血が止まらなくなったりします。適切な輸血をしないと、症状が進行し生命を脅かすこともあります。
輸血は当院でも毎日実施され、1カ月に約100人の患者さんに行われています。特に同種血輸血は、血液を臓器(細胞)とすると『臓器移植』ともいえ、他人の血液を輸血するためアレルギーや感染症の副作用を引き起こす可能性があり、注意が必要です。当院では、安全な輸血療法を行うため、国や各団体から出されている指針・ガイドラインに準じて体制を整えており、施設認定として輸血学会の輸血機能評価認定制度(I&A制度)、国際規格のISO15189を取得し・維持継続しています。 輸血細胞治療部では、院内輸血業務を一元管理しています。『輸血管理業務』(血液センターへ輸血用血液の発注納品・保管管理・払い出し・副作用管理・自己血輸血管理)と『輸血検査業務』(血液型検査・不規則抗体検査・交差適合試験)があります。
輸血前検査は安全な輸血療法には欠かせません。安全を確保するため血液型検査は、輸血する医療機関で実施すること、異なる時点で2回検査して確定することが指針で定められています。緊急時を除き、患者さんと同じ血液型の輸血を使用するため、血液型の確定は重要です。また、交差適合試験は輸血前に患者さんの血液と輸血用の血液を反応させて、本当に輸血しても大丈夫かどうかを確認する検査です。
皆さんは、血液がどこで造られているかご存知ですか?血液は骨の真ん中にある骨髄で造られていて、骨髄には血液のもとの細胞(造血幹細胞といいます)が多くあります。また、赤ちゃんのへその緒(さい帯)にもあります。治療のため骨髄やさい帯血を移植することがあり、骨髄やさい帯血バンクからの受け入れ業務をしています。さらに移植のための末梢血(患者さんの血管を流れる通常の血液)幹細胞採取を医師、看護師と共に実施し、採取後の細胞の処理・保管管理もしています。 輸血療法が常に安全・安心に遅れることなく行われるよう、職員が一致団結し、コミュニケーションを大切に業務に取り組んで参ります。