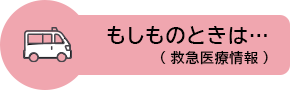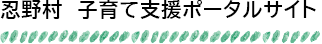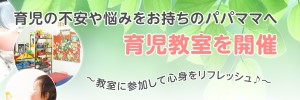本文
膵臓(すいぞう)癌治療の最前線
山梨大学医学部附属病院 消化器外科 特任助教 齊藤 亮
進歩する膵臓がん治療
膵臓はお腹の深いところにあり、おもに消化液を分泌する機能と、血糖のコントロールをする機能を担っています。この膵臓にできる悪性腫瘍である膵臓がんは、日本では男女ともに6 番目に多いがんとなっており、がんによる死亡数では男性で4 位、女性では3 位となっています。山梨県では年間約300 人が膵臓がんと診断されており、70 〜80 歳代の高齢の患者さんが多いことも特徴です。近年では検診制度の普及により、手術が可能な段階で早期発見されることも増えており、また手術の前後に薬物(抗がん剤)治療を行うなど、集学的治療(手術や抗がん剤治療など様々な治療法を組み合わせること)が一般的となりました。その効果もあり、徐々にではありますが、膵臓がんの治療成績は向上しています。我々は内科、外科、放射線科、化学療法部、検査部、コメディカル等が密に連携をとり、ワンチームで膵臓がん治療に取り組んでいます。
膵臓がん手術の最前線
そして、手術においても大きな変換点を迎えています。ロボット手術の台頭です。膵臓がんの手術には大きく分けて、右半分を切除する膵頭十二指腸(すいとうじゅうにしちょう)切除と、左半分を切除する膵体尾部(すいたいびぶ)切除があります。特に前者の膵頭十二指腸切除では、十二指腸や胆管なども一緒に切除し、さらに1 〜2mm 程度の膵管(すいかん)と腸を繋ぎ合わせるなど、非常に細かい再建(さいけん)手技も要求されます。この場面において、ロボットの特徴を最大限に生かすことができます。すなわち、従来の開腹手術を凌駕する正確さでこれらの細かい操作を行うことができるのです。現在ではいずれも術式についても、多くの症例をロボット手術で行っています。ロボットを用いることで、小さい傷で、手術中の出血量が少なく、患者さんの体への負担が小さい手術が可能となります。その結果、高齢の患者さんや併存症を有する患者さんにも、安全な手術を提供することができ、術後の合併症が少なく、今までよりも半分程度の入院期間で退院が可能となっています。
おわりに
膵臓がんに対しては、手術を中心とした集学的治療が行われ、治療成績の向上に取り組んでいます。患者さんにとって負担が少なく、スムーズに社会生活や日常生活に復帰できるよう、最前線のロボット手術を提供して 「リハビリテーション」とは、病気やケガ、加齢などによる後遺症や障害を持つ方が社会復帰を目指すために行う支援のことを言います。そのリハビリテーションに携わる専門職として理学療法士、作業療法士、言語聴覚士があります。今回、言語聴覚士の仕事についてご紹介させていただきます。
私たちはことばによってお互いの気持ちや考えを伝え合い、経験や知識を共有して生活をしています。ことばによるコミュニケーションには言語、聴覚、発声・発音、認知などの各機能が関係していますが、病気や交通事故などが原因でこのような機能が損なわれることがあります。ことばによるコミュニケーションの問題には失語症や高次脳機能障害の他、聴覚障害、ことばの発達の遅れ、吃音、声や発音の障害など多岐に渡り、小児から高齢者まで幅広く現れます。それ以外にも飲み込みが難しくなる(摂食嚥下障害)こともあります。また、近年、加齢性難聴によるコミュニケーション障害が社会的孤立やうつ病を引き起こす要因になり、難聴が認知症の発症のリスクを高めることも明らかになってきています。人が幸せに生きていくために欠かせない「話す・聴く・食べる」ことへのリハビリに特化した専門職が言語聴覚士です。
言語聴覚士は医療施設だけでなく、介護・福祉・保健施設、教育機関など幅広い領域において活躍する場があります。山梨県には約120名(山梨県言語聴覚士会会員数)の言語聴覚士がいますが、まだ理学療法士や作業療法士に比べ人数が少なく、言語聴覚士がいない地域もあるため、十分な関わりが出来ていない状況にあります。しかし、山梨県言語聴覚士会では困られている方に対して真摯にサポートできる体制がありますので、コミュニケーション障害、摂食嚥下障害などでお困りの場合は気軽にご連絡下さい(連絡先は山梨県言語聴覚士会ホームページ<外部リンク>を参照)。
日本は2025年に超高齢化社会を迎えると想定されています。高齢者が増えると飲み込みの障害や加齢性難聴、認知症によるコミュニケーション障害を患う方が増える可能性が高くなると予想されます。人生の再スタートに関わる意義のある仕事だと思いますので、言語聴覚士の仕事に興味を持って頂けますと幸いです。